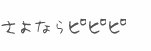|
『おはよう一平くん。 起きてた?』
「んん、あぁ、おはよう…今、起きた。」
『じゃあ、切るね? 二度寝しないでよ。』
「ん。わかった。ありがと。」
『それじゃ、いってらっしゃい。』
「亜矢子も、仕事がんばれよ。」
『ん…そっちもね。じゃあね。』
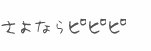
《 1 》
彼女の電話で目覚める朝は、いつも甘やかな幸福に満ちていた。
二日酔いの朝も、寝不足の朝も。 そうじゃなくなったのは、いつからだったのだろう。
ほぼ半年ぶりに会う約束をして、彼女の実家近くまで車で迎えに来た僕は、約束の時間が近くなるにつれて、居心地の悪さを感じていた。
約束の時刻は、午後3時。 待ち合わせは、いつもの公園のベンチだった。
彼女を待つ間、思考を空っぽにして、晴れた空に泳ぐ鰯雲を眺めていた。
時折吹く薄寒い風に、知らずに深まっていく秋の気配を、ふと感じる。
公園内の景色は、半年前と何も変わらない。 遊具の位置は変わらないし、トイレの外壁は相変わらずくすんだような緑色をしているし、パンダのスプリング遊具は、白目を剥いている。
違うのは、青々とした緑を湛えていた桜の木々が、ゆっくりと葉の色を変えている事と、蒸れるような新緑の匂いが、金木犀の甘い香りに取って代わったことくらいだ。
一番に変わってしまったのは、二人の気持ちだろう。
約束の3時を過ぎ、公園の入り口に見えた亜矢子の姿を眺めながら、何となくそんな事を考えていた。
『ごめーん、遅くなっちゃったー』
彼女はいつもおどけた表情を浮べて、約束よりも遅れてやってくる。
『あんたねー、どんだけ待たせんだよ。待ちくたびれたぞ。罰としてジュースを奢れ。』
僕はいつもそれに腹を立てて、無愛想に彼女を迎える。
『いいけど、じゃあ一平くん晩御飯奢んなさいよ』
自分勝手はいつもの事だ。
だけどそんなやり取りが楽しくて、僕はついつい乗せられてしまう。
『仕方ねーなぁ…って、何それ!? 単価が全然ちげーだろ。 バカか!』
「ごめん。 遅くなっちゃった。」
「…いや、いいよ。」
ほぼ半年ぶりに会う亜矢子は、以前と、少し変わって見えた。
長かった黒髪は肩までの茶髪になって、化粧も少し濃くなったように感じた。
僕の知らない服を着た彼女は、前よりも色っぽく見えた。
彼女は、歩行者を警戒する野良猫のような、どこか余所余所しい雰囲気を、纏っていた。
それは彼女からすれば、多分、僕も同じなのだろう。
お互いを警戒しながらも、できるだけ意識しないように、さりげなくさりげなく道を横切っていくように。 僕達は言葉も少なげにベンチから立ち上がると、駐車場に向かって歩き出した。
僕達は、大学の先輩と後輩で、付き合い始めたのは、僕が2年生、亜矢子が1年生の夏だった。
付き合い始めてから、丸6年と2ヶ月が経つ。
一緒に大学で過ごしたのは3年間で、僕が全国で営業している大手メーカーに就職してからは、遠距離恋愛を続けていた。
駐車場にたどり着いた僕達は、お互いに目を合わせようとしないまま、車に乗り込んだ。
「さて、どこにいこう。」
ナビを見つめたまま、彼女に声をかける。
妙に上ずった声が出る。 空元気だ。今日の予定は、何も考えていない。
「どこか、座れるところにいこうよ。千尋さんの店とか。」
少し固い声で、亜矢子が返す。
場所、覚えてるよね?
という亜矢子の声に、胸になにかつかえるものを感じながら、僕は、短い返事を返して、エンジンを始動させた。
―――『ごめん。別れたい。』
先週の終わり。 真夜中に、亜矢子からメールが届いた。
雨の金曜日だった。 まだ会社に残っていた僕は、喫煙所に立って、そこから彼女に電話をかけた。
来週末に帰るから、その時に話をしよう。
いつもの公園に迎えに行くと言うと、彼女は感情の読めない声色で、わかった、と返事をした。
その時は、一通のメールで終わりにしたくないと思って、咄嗟に約束を取り付けたものの、短い言葉のやりとりはそれで終わり、次の日も、その次の日も、結局今日まで、それ以上の言葉を交わすことはなかった。
週末を待つまでの間、重苦しい気分になったが、どうにかしようという気持ちは湧いてこなかった。
どうして別れるなんて言うんだ? そんな疑問を口にする事がもう、白々しいと感じた。
定期的に連絡を取り合わなくなってから、もう何ヶ月も経っている。
結局何も行動にしないまま、僕は今日を迎えた。
窓の外を流れていく見慣れた町並みに目をやりながら、僕は車を走らせた。
FMラジオの音楽は、流行のポップミュージックを流している。
会話の無い車内に、その明るいメロディは軽々しく漂っては消えていく。
付き合う前は、亜矢子とはよく音楽の話をしていた。
付き合った後も、二人でよくカラオケに行ったっけ。
僕は、大学2年の夏、告白しようと決意して、家の車を持ち出し彼女とデートした時の事を、ふと思い出した。
彼女の好きな曲を、こっそりとメールでリクエストしたのだ。
《今、好きな子とデートしながら聞いてまーす、とリクエストを下さったのは、
浦和区のラジオネーム“焼きそば君”さん。 いいなー、楽しんでね。
曲は――》
夏の夕方、突然そのメールは読み上げられた。
リクエストしたのは、当時、亜矢子が大好きな曲だった。
それは、リリースされて日が経っていたので、あまりオンエアされない曲だった。
なんてラッキーだろう、と僕がしめしめ思っていると、ふいに亜矢子はくすくすと笑い出した。
曲が終わり、CMに入ったところで、彼女が僕を見た。
『ねえ、ひょっとして、今のリクエストって、一平くん?』
僕は、動揺した。
『えっ、なんでわかった?』
『ラジオネームが焼きそば君だったから、もしかしてと思って。』
亜矢子は、可笑しそうに声を出して笑った。
『焼きそば君って、ねえ。』
そして、目じりに浮かんだ涙をそっと指で隠した。
「・・・・・・。」
赤信号でブレーキをかける。ラジオ番組はCMに入り、トラフィックインフォメーションが流れている。
何か話すべきだろうか。
僕は沈黙が気になり、言葉を捜した。
しかし、「別れたい」から先の言葉を、亜矢子はまだ、一言も口にしていない。 今、当たり障りの無い話題など、あるはずもなかった。
あそこのコンビニつぶれたの、とか、そんな話題しか思い浮かばない。
「青だよ」
「あ、ごめん。」
亜矢子の声で青信号に気付き、あわててブレーキから足を離した。
同級生の柳千尋の家業である喫茶店『やなぎ屋』は、随分様変わりしていた。
僕の知っている『やなぎ屋』は、風通しの悪そうな古びた喫茶店だったのに、知らない間に新築と見違えるような大改修が施されていた。
さながら、お洒落なカフェといったところだ。
一瞬、場所を間違えたかと肝を冷やした。
近くのパーキングに車を停めて店の戸をくぐると、聞きなれた「いらっしゃいませー」という元気な声が聞える。
地味なエプロンを身に着けた女性は、僕と同級生の柳千尋だった。
「あれっ、仁科一平?」
千尋もすぐに僕に気が付く。
「ひさしぶり。いきなり客をフルネームで呼び捨てかよ。」
いつもの事じゃないの、と笑う千尋に、僕はいくらか調子を取り戻す事ができた。
よく言えばアンティーク、悪く言えばごちゃごちゃしていて、薄暗くて、ちょっと不気味だった前の内装に比べて、改装後の店内は余計なものが一切なく、カウンターも、テーブルも、全て塗装されていない天然の木の什器で統一されている。
よく見ると看板が、知らない間に『自然食カフェ やなぎ屋』に変わっていた。
「随分綺麗になったなぁ」
店を見渡しながら、つい、思っていた事が声に出る。
「あ。お店の事ですよ? 相変わらず、お客さんはあんまりいないけど」
「余計なお世話です。 ちょっと前に、リフォームしたのよ」
ランチタイムは混むんだから。おやつ時でよかったわね、と千尋は軽い調子で返す。
「親父さんとお袋さんは元気?」
「ええ。」
後ろから、亜矢子が僕の腕に触れる。
「…一平くん、」
入り口で突っ立ったままの僕を、控えめに亜矢子が促した。
「悪い、座ろう。」
テーブル席は、改装した後も変わらない配置でそこにあった。
右奥のテーブル席は、僕と亜矢子のお決まりの席だった。 学生の時から、この喫茶店にはよく来ていて、その時から、二人の時は大体、この席だ。
小さな花の飾られた窓際のこの席で、いつも僕はコーヒーを頼み、亜矢子はアイスティーとミルクレープをワンカット頼む。
初めてのデートもこの席だった。
ガードの固い亜矢子に、『サークルの先輩ん家がやってる喫茶店なら、二人で行っても大丈夫でしょ』と、苦しい文句を言いながら、僕は亜矢子とこのテーブル席に腰掛けたのを覚えている。
「ご注文は?」
二人の前にお冷とお絞りを並べると、千尋が伝票を手に問いかけた。
僕達の雰囲気を察知して、「いつもの?
」という言葉を飲み込んだのだろうか、喉になにか詰まったみたいに一瞬言葉を切らせて、
「まだなら、また後で聞くけど」
と笑顔を見せる。 僕は、いつもどおりを装って、
「あ、いいよ。 ブレンドをひとつと――」
亜矢子をちらと見る。 亜矢子が注文の続きを受け取った。
「あ、すみません。 ふたつで。」
「ブレンドふたつね。
何、今日はケーキ食べてかないの?」
亜矢子は掌を振って見せて、頷いた。
「はい、今日は私、このあとちょっと用事があるんで。」
あれ、そうだったのか。
そんなこと言っていなかったので、少し驚く。
僕は、まあ、そうか、と思い直した。
別れ話は、コーヒー一杯で済むらしい。 そしたら彼女は、多分、店を出て行くのだろう。
それならわざわざ、千尋の店で無くたってよかっただろうに。
亜矢子の苦笑いに、千尋はまた一呼吸をおいて、
「そう、わかった。
それじゃあ少々お待ち下さいね。」
笑顔を残し、カウンターに戻っていった。
千尋がカウンターの中に戻ると、また僕達の間には沈黙が漂い始めた。
今日、彼女を正面から見る事を避けていた僕は、初めて彼女と向かい合った。
「………。」
爪のマニキュアが、綺麗だった。
少しうつむいた彼女の視線は、お冷のグラス辺りに向いている。感情の伺えない表情は、しかしどこか哀しそうだった。
「………。」
僕はその表情に、見覚えがあった。 彼女のこんな表情を見るのは、初めてではなかった。
就職活動で悩んでいたとき、彼女は今日のような顔をしていた。
地元の地方銀行と、大手企業の2つの内定を貰ったときだ。
『どうしよう、一平くん』
地銀なら支店ごとの転勤はあるけど地元を離れなくても良い。だけどもう一方は、総合職だから転勤もあり得るのだと、亜矢子は言った。
『これ以上離れちゃったら、もう、めったに合えないもん。』
彼女の様子を見て、僕は思った。 自分と別れたいと切り出した彼女は、まだその言葉に迷っているのではないか。
「一平くん、ごめん。」
まっすぐに視線を合わせて、亜矢子が言った。
小さく唇を噛んで、絞りだすように。
「好きな人ができたんだ。」
「……。」
僕は、「そうか。」と一言返すことしか出来なかった。
作り笑いを浮べて、その先を促す。
「銀行のひと?」
「…うん。」
少し、震える声で、彼女が頷く。
「そうか。」
また、「そうか。」
心の中で、自分自身に舌打ちをする。こんなとき、なんと言っていいのか、わからなかった。 亜矢子は、弱弱しく微笑んだ。
「ごめんね、私、遠距離でも続けていけるって、自信あったんだけど。」
「うん。」
「ダメだったみたい。ほんと、申し訳ない。」
少しおどけて、小さくお辞儀をする。
停止を始めた思考で、僕は、これでいい。
と静かに肯定した。
もし彼女が別れるかどうかを悩んでいたとして、僕に意見を求めたとしても、結局結果は変わらなかった。今のままの関係をダラダラと続けるよりも、このほうが、彼女にとっても、僕にとっても、きっと良いに決まっている。
「コーヒーをお持ちしました。」
注文していたコーヒーを、千尋がトレイに載せて運んできた。まず亜矢子のコースターにカップをのせ、次に僕のコースターにカップを乗せ、伝票をテーブルの端に裏返して置くと、
「なぁに、あんた達えらく辛気臭い雰囲気じゃないの」
ふう、と、止めていた息を吐き出すようにして、言った。
「ああ、千尋さん。
私たち、別れる事にしましたので。」
明るい調子で、亜矢子が苦笑いする。
「えっ、何? そうなの?」
僕も頷いて、冗談を言った。
「失恋記念に、ケーキを奢ってくれよ」
「いいの? そんな軽くて」
千尋は困惑したような苦笑いを、亜矢子に向けた。
それから、細い、据わった目を僕に向けて、返事をする。
「ケーキが食べたいなら、480円からです。 おごりません。特にあんたには。
アヤちゃん、アヤちゃんはこいつのツケで注文してもいいんだよ。」
「どういう事だそれ」
「いいです、いいです。」
亜矢子は苦笑いで、手を振った。
軽いノリが戻ってきて、僕は内心、少しほっとしていた。
《 2 》
僕が亜矢子との関係について、何となくもうダメかもしれないと思い始めたのは、半年ほど前からだった。
毎朝、亜矢子がかけてくれていたモーニングコールが、ある日突然掛かってこなくなったのだ。
いつも、都合が悪い日は前もって連絡をくれていたのに。
その日は会社に遅刻して、亜矢子に対して、怒りを覚えた。
しかし、夜になると冷静になって、別に彼女は目覚まし時計じゃないし、母親でもないのだし、電話をくれないからといって怒るのは筋違いだろうと思い直した。
喧嘩になるといけないと思い、その日はメールも、電話も、しなかった。
次の日も、その次の日も、電話は来なかった。
それがしばらく続いて、僕は自分の日常から、亜矢子がだんだんと薄れていくのを感じるようになった。
会社から“初任地は大阪だ”と辞令を渡された時は、二人して落ち込んだものだ。
遠距離恋愛になる直前に、僕は自分名義で、家族割りの効く携帯電話をもうひとつ契約し、亜矢子に手渡した。
それまでは、住んでいた部屋が亜矢子の実家のすぐ近くだったので、会おうと思えばいつでも会えたけれど、遠く離れるのだから、割引の利く携帯電話は必須だったのだ。
『毎日電話してもいいの?』
『仕事終わるの、夜中になっちゃうからなあ。 毎日は、亜矢子もしんどいだろ。 別に、無理して電話くれることないよ。』
『クールぶっちゃって!
さびしいくせに。 あ、そうだ。 じゃあ朝、電話で起こしてあげよっか。』
彼女の電話で目覚める朝は、いつも甘やかな幸福に満ちていた。
自分だって朝弱いくせに。
電話でおはようと言う眠そうな声に嬉しくなって、僕は二日酔いでも、寝不足でも、毎日頑張ることができたように思う。
遠く離れていても、おやすみのメールと、目覚ましの電話は欠かさないように、僕達は毎日を過ごした。
お互いの気持ちがはなれていく事を気にする事なんかよりも、ただ毎日、自分がそうしたくて連絡を取り合った。
――はじめの一年半は。
僕の仕事は月日を経るごとに量を増し、また、僕自身も、課された責任と、期待に応える事に、楽しさを覚えるようになった。
職場の中での悩みは、いつだって、それなりにある。
しかしそれを亜矢子に相談する事は、しなかった。
亜矢子とは、楽しい話題だけ、話していたかった。
自分がそう思うから、亜矢子が友達と喧嘩した愚痴を電話で聞かされても、僕はあまり真面目に取り合う事をしなくなった。気になるのは、それよりも眠いこと。
明日も朝が早いこと。
そんな毎日が少しずつ、二人の溝を広げていったのだろう。
彼女の事を考える時間は徐々に減っていき、いつしかその存在は希薄になっていった。
亜矢子が目覚ましの電話をやめたのも、きっと同じだろうと僕は思った。
だから、それ以降は自分の携帯の目覚まし機能を使い、自力で目覚めるようにした。
だから、本当のところはお互い様なのだ。
僕はもう、亜矢子のことが昔ほど好きじゃない。
亜矢子もきっと同じなのだろう。
そして彼女は、そうして気持ちが薄れていく中で、他の誰かを探した。
自然消滅しそうなこの関係を続けていく事は不毛に違いなく、本当は自分が潔く別れを切り出すべきだったのだろうと思う。
そう頭では理解できているのに、いきなり好きな人が出来たって言われても、と思う気持ちもあって、僕は彼女の言葉に、素直に応える事ができなかった。
「ごめんね」と謝った彼女に、謝る事をあえて、しなかった。
「じゃあ私、そろそろ行くね。」
注文したコーヒーが無くなる頃、時計を見て、亜矢子はバッグから財布を取り出した。
「送ってくよ。」
「大丈夫 大丈夫。 一平くん、千尋さんとも会うの久しぶりだろうし、ゆっくりお話でもしていきなよ。 駅、すぐそこだから。」
「なら、勘定は俺が持つよ。」
立ち上がる僕に、亜矢子は少し寂しげに微笑んだ。
「ありがとう、じゃあ、ごちそうさま。」
亜矢子は、バッグから白い携帯電話を取り出した。 それは、僕名義の携帯電話だった。
いつも二人を繋いでいたそれは、3年以上が経った今でも、少し塗装が剥げているのを除けば、綺麗なままだった。
「これ、返すね。 ごめんね、ちょっと汚れちゃったけど」
携帯電話を受け取りながら、僕は、胸が苦しくなるのを感じた。
これでもう最後だというのに、交わす言葉が見つからない。
僕の言葉を待つことなく、亜矢子は、
「一平くん、今までありがとう。」
そう言って笑って、店を後にした。
亜矢子が出て行く頃、店内にはもう、僕の他に客はいなくなっていた。
僕は亜矢子のコーヒーカップと自分のコーヒーカップを手に、カウンターに席を移動した。
もう少し、誰かと話をしていたい気分だった。
ふたつのカップを千尋に手渡し、「俺のはお代わり」と注文すると、千尋は睨むような視線を飛ばして、ぶっきらぼうに、
「まいどあり。」
と奪うように僕の手からカップをもぎ取った。
その態度が癇に障って、僕は千尋を睨みかえす。
「なんだよ、なんか怒ってんのか?」
返事には、溜息がついている。
「あたしが怒ることじゃないよ。」
「何?」
「フン」
鼻を鳴らして背を向けると、千尋はお代わりのコーヒーを淹れはじめた。
(なんだ、こいつ。)
他に客のいなくなった店内は、静かなものだった。
BGMが掛かってなければ、時計の音まで聞えてきそうだ。
僕は、むかむかとした気持ちのまま、亜矢子が出て行ったばかりのドアを眺めた。
ガラス窓の外では、知らない間に流れてきた雲が、太陽を隠している。
薄暗い空の下を、寒そうな風が駆け、通りの向かいの並木を揺らしていた。
6年付き合った彼女と別れたばかりだというのに、同級生に喧嘩を売られてイライラしているだなんて。 僕は、内心で苦笑いをする。
本当はもっと、後味の悪い別れ方になると思っていた。
亜矢子は泣き虫だったから、僕が別れようなんて言いだせば絶対泣くと思った。
それを嫌ってあえて『そのまま』を続けてきたわけではないけれど、僕を責めようともせず、涙も見せず、さよならも言わず、ただ寂しそうに笑って『ありがとう』と言われる別れ方なんて、予想だにしていなかった。
なんだか、別れた実感がなかった。
「はい。お代わり。」
「…ありがと。」
相変わらずぶっきらぼうな千尋に何とか御礼を言って、僕はコーヒーを一口飲んだ。
これしきの事で、『ありがとう』というのは躊躇われるものなんだな、と思う。
亜矢子は、どんな気持ちでそういったのだろう。
もうすっかり思考をやめた頭では、そんなぼんやりした自問が、浮かんではうっすらと消えていった。
「……。」
「……。」
明日は、また朝早いんだ。
今日はもう実家に寄るのはやめて、車を飛ばして自宅に帰ろう。
また何時間も高速か。 あー、めんどうくさいな。
「だめだ。 あんたみてるとなんか腹立ってくる」
いきなり発せられた一言に、僕は、千尋を見た。
千尋はエプロンの肩紐を腹立たしげに掻きながら、僕を睨みつける。
「なんだよ、いきなり。」
「アヤちゃんのことだよ。」
「何?」
「本当に別れていいの?
あんな良い子ほかにいないよ。」
やっぱり、その事で怒っていたのか。
僕は小さく息をついて、もういいよ、と言った。
「本当ににいいの?」
「…やけに突っかかんな。」
千尋は千尋なりに、思うところがあるのだろう。 それはわかるけれど、これは僕達の問題だ。
知り合いだからといって、干渉されるのは、不愉快だった。
千尋もそれくらいわかっているだろうに、らしくもなく絡んでくる。
「こんなこと言っちゃ、亜矢子ちゃん怒るだろうけど。
…あの子、まだあんたの事好きだと思うよ。
なんで別れちゃうの。」
僕は思わず、まさか、と笑ってしまう。
「……あいつ、会社に好きな男がいるって言ってたよ」
「少なくとも私は、そんな話、聞いたこと無いね。」
「聞いてねぇだけだろ。」
彼女は必死に食い下がる。
「亜矢子ちゃん、時々、この店にひとりでやって来てたんだよ。 で、いつも同じもの注文して…」
千尋は、デザートの冷蔵ケースの一番右下に視線を向けた。
ミルクレープと、アイスティー。
「それを、寂しそうにひとりで食べながら、何にも言わないんだもの。
何悩んでるのか、気になっちゃうじゃないの。
だから無理やり聞いたんだよ。
そしたら、何、ずっと音信不通だって?
あの子、あんたの悪口一言も言わないもんだから――」
そこまで言って、千尋は、大きな溜息ついた。
「…なんで、マメに連絡とってあげなかったの。」
「ごめん。」
「…私に謝ったって、意味無いよ。」
千尋は、泣き出しそうな顔で、俯いた。
「仁科はもう、アヤちゃんの事好きじゃないのね。」
カランカランと、ドアのカウベルが、来客を告げた。
複雑な視線で僕を一瞥して、千尋は接客顔を浮かべて入り口の方を向いた。
「いらっしゃいませ、何名様でしょうか?」
僕は飲みかけのコーヒーをそのままに、席を立った。
お会計を済ませ、車に乗り込み、自宅への帰路についた。
《 3 》
薄いカーテン越しに、新しい朝の光が室内を照らす。
『おはよう一平くん。 起きてた?』
「んん、あぁ、おはよう…今起きた。」
『じゃあ、切るね? 二度寝しないでよ。』
「ん。わかった。ありがと。」
『それじゃ、いってらっしゃい。』
「亜矢子も、仕事がんばれよ。」
『ん…そっちもね。じゃあね。』
彼女の声で目覚める朝は、いつも甘やかな幸福に満ちていた。
忙しい朝も、寝不足な朝も。そうじゃなくなったのは、いつからだったのだろう。
まどろみの中で僕は、懐かしい夢を見ていた。
亜矢子が部屋に泊まりにくるときは、いつも晩御飯の担当を賭けて、勝負をしたこと。
『晩飯の担当を賭けて、しりとりカラオケで勝負しようぜ!』
『アルファベット曲はあり?』
『ありです。洋楽もOKです。』
『悪いけど、今度はあたし負けないからね。B’zを特訓した今となっては、一平くんなんかおそるるにたりませんよ。』
『言ってろ。な行攻めでギャフンと言わせてやるよ』
負けず嫌いの亜矢子を負かしても何もメリットはないのに、ついつい必死になってしまうこと。
『悔しい…』
『ははは、ミスチルとスピッツとサザンを全曲覚えてる俺に大口叩くとか、無謀ですな。
無謀。 さて、じゃあ とっととカレーの材料買って帰るか』
『…カレーでいいの?』
『あんたそれしか作れないでしょ。』
『し、失礼な!』
デートで遠出すると、大抵いつも亜矢子が足を引っ張ること。
『せっかく車で遠出だってのに、朝から犬のフン踏んでくるとか、ツイてるね亜矢子さん。』
『すんません…』
『っていうか、バカでしょ?
次は車に乗る前に言ってくれるかね。
そうやって不自然に浮かせてる左足から、なんとも言えないニオイがこうツーンときてるんだけど。』
『ほんと、すんません…』
『……いーよ、もう。 次のサービスエリアで靴洗ってやるから、もうちょっとその体勢で我慢してな。』
二人して落ち込んだこと。
『あー、最悪だー。 初任地が大阪なんて。』
『転勤、あるんだよね?』
『あるけど、5年は今の部署だと思う。』
『はぁー、そっか。』
『ああー。』
『ツイてるね…』
『ツイてるわぁ…』
『別れようとか、言わないよね?』
『何言ってんの、言うわけないだろ。』
『よかった…。』
『あ、そうだ。家族割りの効く携帯買ってきたんだよ。あんたこれ、持ってなさい。』
『…ありがとう。』
『何? 亜矢子さん泣いてるの? 老人じゃあるまいし、ちょっと涙腺弱すぎるんでないの?』
『五月蝿いな。』
『これからはさ、これでちょくちょく連絡取り合っていこうや。』
『毎日電話してもいいの?』
『仕事終わるの、夜中になっちゃうからなあ。 毎日は、亜矢子もしんどいだろ。 別に、無理して電話くれることないよ。』
『クールぶっちゃって!
さびしいくせに。 あ、そうだ。 じゃあ朝、電話で起こしてあげよっか。』
『いや、無理でしょ。 朝弱いでしょ、亜矢子』
『まあ、見てなさいって。
一平くんも、一日の始めに可愛い彼女の声が聞けたら、嬉しいでしょ?』
『自分で可愛いとか言っているのが、気の毒だよね』
『あー、そんじゃーもう絶対起こしてあげない』
『嘘ですー、お願いしますー』
大学で一緒に過ごした3年と、遠くに離れていた3年が、バラバラに夢に出てきた。
楽しくて温かな思い出、喧嘩して痛い目をみた思い出、それらは一瞬強く心に映っては、浮かび上がった瞬間、泡のように、すぐに弾けて消えていった。
僕の6年にわたる恋は、昨日、終わった。
泣き虫な亜矢子は、僕を責めようとはせず、涙も見せず、ただ寂しそうに笑って、『今までありがとう』とだけ言葉を残した。
僕にとって、そんな別れは少し予想外だった。
そのせいか、昨日は家に帰ってきても、実感のないまま、眠りに付いたのだ。
喪失感の無いことに、ショックを受けていた。
『ピピ・・・ ピピピピ・・・ ピピピピ・・・』
朝日が昇る頃、けたたましいアラーム音に僕は呼び起こされた。
薄目を開いて、枕元で充電中の携帯電話を掴む。携帯電話はいつもと同じ6時を表示している。
停止のボタンを押して、気が付いた。
『ピピピピ・・・ ピピピ・・・ ピピピ・・・ 』
音が鳴り止まない。
音を立てているのは、僕の携帯電話だけではなかった。
『ピピピ・・・ ピピピ・・・ 』
昨日返された、亜矢子の携帯電話を思い出し、僕はベッドから起き上がった。
どんどんと音量を増すアラームに、苛立ちを覚える。
昨日使った鞄を掴むと、中を探って、乱暴に白い携帯電話を取り出した。
舌打ちをして、二つ折りの携帯電話を開く。
その時、アラームのアニメーションと一緒に、画面に表示された短いアラームメッセージが見えた。
僕は、目を見開いた。
『早く起きないと、一平が遅刻する!!』
赤い、『!』マークの絵文字が、ふたつ、並んでいた。
このアラームで目を覚まし、眠気眼で電話を寄越してくれる亜矢子の姿が、まぶたに浮かぶ。
彼女は、今もまだ、このアラームで朝、目を覚ましていたのだろうか。 千尋が言った言葉が、頭をよぎった。
アラーム設定を見れば、10分刻みに、いくつも時間が設定されていた。
『二度寝厳禁! 6:15』
『ここで起きないと、一平の遅刻確定 6:25』
それを見た瞬間、苛立ちを誘う雑音にしか聞えなかったアラーム音が、まったく違って聞こえた気がした。
その音は、僕の鼓膜に、はっきりと意味を成して、聞こえた。
『まあ、見てなさいって。
一平くんも、一日の始めに可愛い彼女の声が聞けたら、嬉しいでしょ?』
喪失感とも、寂寥感とも言える気持ちが胸をふさぎ、僕はそこで初めて、この恋が終わったのだと感じた。
千尋が言っていた事が本当かどうかはもう、確認する術がない。
確認したところで、何も変わりはしない。
――だけど、本当は自分から彼女に謝らなくてはいけなかったのだと、僕は強く後悔した。
『ピピピ・・・ ピピピ・・・ ピピピ・・・』
スヌーズ機能で、再び鳴り出したアラームの音が、部屋中に響く。
僕は、しばらく携帯電話を握り締めたまま、そのアラームを止めることが出来ずにいた。
2010.11.02
Update.
|