|
動機はくだらないジンクス。
たのみは3位の星占い。
だけど、プロポーズはプロボーズだ。
口に出してOKをもらった瞬間から、二人は。
恋人という肩書きから、婚約者に変わってしまう。
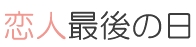
「貴博さん、起きて。」
耳元で聞こえる、笑うような声に安眠を邪魔されて、僕は寝返りをうった。
「あぁ・・・休みなんだから、もうちょっとだけ寝かせてくれ。」
起きる気がないのを伝えると、小さな手の置かれた僕の肩が、震度3の揺れを観測した。
「朝ごはんが冷めちゃうわよ。 ほら、早く起きて。」
彼女は困ったように笑って、どんどんと震度を上げてゆく。
「わかった、わかった。 起きるよ。」
震度6で、ついに僕は目を覚ました。
小動物みたいに軽い足取りでキッチンへと戻っていく彼女の跡を、冬眠明けのクマよろしく、のそのそと歩いてつづく。
「君もたしか今日は休みだったよね。」
「ええ、そうよ。」
休みの日も早起きな同居人のおかげで、
モーニングコーヒーには、甘く温かな、いい匂いがする。
テーブルには四つにたたまれた朝刊と、二人分のコーヒーカップ。
僕が新聞を広げると、彼女は僕のカップに入れてあったお湯を流して、そこへコーヒーを汲んでくれた。
キッチンテーブルの上に置かれたボウルを見て、今朝のメニューに気づく。
「へえ、パンケーキ?」
「ええ、そうよ。 フライパンでつくるやつ。」
「子供の頃以来だなぁ。」
「たまにはいいでしょ?」
嬉しそうな笑顔をのこすと、奈津子さんはまたまわれ右して、キッチンに向かった。
フライパンと火をつかった料理をしているので、声をかけないほうがいいのはわかっているんだけど。
こちらをむいて欲しくなって、ついつい気を引いてしまう。
「パンケーキは嬉しいけど。 冷めるなんて言って、まだ出来てないんじゃないか。」
目の下まで持ち上げた新聞紙で半分顔を隠して、ぴんと背の伸びたうしろ姿を見つめる。
手際よくバターをフライパンに落として、こちらを振り向かない返事が返ってくる。
「もうちょっとでできますよ。 先にシャワーでも浴びてきたら?」
「おなかがすいた。
すぐ食べられると思ったから、起きてきたのになあ。」
席を立って、そっと後ろからしのびよる。
「もう、屁理屈言わない。」
そう言いながら振り向こうとした彼女の背中を、後ろからだきしめて、だだっこのようにうなじに顎をのせてみる。
くすぐったそうに笑いながら、彼女は悲鳴をあげた。
「貴博さん、いたい、いたい!」
「え、痛い?」
予想外な感想にあわてて手を離すと、奈津子は胸をトンと叩いて、
「髭が痛いっ。」
はっと気が付いて顎に手をやると、昨晩剃ったはずのひげがもうしっかりとしていた。
彼女は怒ったように、人差し指を突きつけて。
「やることがないなら、まず洗面所に行く!」
赤い顔で言われちゃ、迫力もないけれど。
顎に手をあてて反省した。
「そうします。」
「顔も洗ってくること!」
「はい。」
にやにやしていたらまた怒られるだろうから、さっさと後ろを向いてから、僕は笑った。
毛先の開いたピンクの歯ブラシを口に突っ込んで、歯を磨く。
洗面台にある歯ブラシとマグカップは、お揃いではない。
だけどたしかに2色分。
恋人らしいベタベタをあまり好まない彼女は、シンプルな紺の歯ブラシと紺のマグカップ。
顔に似合わないとかよく言われるが、僕のは両方ともピンクでそろえてある。
何も知らないひとが見たら、多分間違えるだろうな。
がしがしと歯を磨きながら、瞼に残ったあとすこしの眠気を払い取る。
習慣的になってしまったものは、うっかりその存在を忘れてしまいそうになるけど、半年前は紺のマグカップも、歯ブラシも無かったし、実を言うと掃除機も、まな板もなかった。
冷蔵庫の中はビールと冷凍食品しかなかったし、そう考えると、今の生活はまるで夢のようだと思う。
同時に、苦笑いがこみあげてくるのだ。
奈津子がこの部屋に住むようになってから、もう半年。
彼女が買おうとねだったものは、日用品ばかりだ。
金品アクセサリーを買ってと言われたことなど、一度もないから不思議で仕方ない。
頼まれもしないのに買ってみた指輪は、今も秘密のへそくり置き場で、登場の日を待っている。
恋人として過ごした年月は、もうかれこれ4年と約半年。
そろそろ頃合かな、なんて。
学生時代に流行っていたジンクスを思い出して笑う。
プロレス技かけるのをゆるしてくれたらセックスを迫ってみてもOKで、
二人っきりの時のオナラをゆるしてくれたら、婚約を切り出してもOKだって。
もよおすたびに柄にもなくこそこそと席を立つ僕は、
もしかしたら返事を聞くのが恐いただの臆病者なのかもしれないな。
テーブルに戻ると、そこにはキツネ色に焼けた大きなパンケーキが出来上がっていた。
テーブルの真中の大皿に置かれた大きなパンケーキには、取り分けられるようにナイフと小皿が添えてある。
控えめな、甘い香りが鼻をくすぐった。
「うまそうだな。」
「食べてみて?
ちょっとお砂糖入れすぎちゃったかも。 甘すぎないかなぁ。」
取り分けたパンケーキにメープルシロップを豪快にそそいで、フォークでそれを口にほうりこんだ。
「うまいよ。」
「甘すぎない?」
「丁度いいよ。ありがとう。」
僕をみつめて、それから一瞬だけ。 照れたように奈津子は笑う。
「どういたしまして。」
テレビをつけると、普段は見ることが出来ない朝のワイドショーが賑やかな音楽を奏でている。
「最近仕事はどう?」
「ぼちぼちかなあ。特に変わったことはないわよ。そっちは?」
「うちのオフィスのあるフロアが全面改装になったよ。 丸ごと部署が移動したんだ。」
「大変ねぇ。」
「でもそのかわり、移動した先が7階の改装後のフロアーでね。 壁も張り替えたばかりで、きれいなもんだよ。 デスクもパーテションで半個室になって、広い広い。」
「快適なの?」
「うん。」
大袈裟に拗ねたフリをして、少し投げやりに奈津子が笑う。
「それでいつも帰りが遅いんだ。 仕事星人ね。」
まるで新婚さんみたいだ。 照れくさいやりとりに、僕も笑う。
そうなればいいと願うけれど、まだ行動は起こしていない。
お互いの休みの日が合うのは珍しく、今日はチャンスなのだ。
お互いの休みの合う今日という日を、僕はひと月も前から狙っていた。
明日こそは。 そう思って、昨日は眠りについた。
君の好きな芸術展も下調べ済み。 たしか4月末まではルノワール展。
知人のやってるレストランに予約も入れた。
今までもチャンスはたくさんあったけれど、言い訳をすれば、お互いの都合が合わない事も多かった。
そしてあと一歩、踏ん切りがついていなかった。
テレビに目を向けると、丁度朝の星座占いが始まるところだった。
毎朝テレビをつけているけど、これが始まるまでに家を出ているので、随分久しぶりに見る気がする。
「お、久しぶりに見た。」
「そうねー、貴博さん、いつも朝が早いから。」
占いなど当てにならない。と大人ぶってはいるが、僕は結構占いなどを気にする方だ。
「とはいえ、あまり好きじゃないんだよ、こういうの。」
順位が低かったら、士気が下がる気がする。
なんて言ってしらん顔をしながら、ちらちらと横目で見ていたら、
「貴博さん、さそり座、3位。」
奈津子は可笑しそうに笑って、コーヒーを注ぎ足すついでに教えてくれた。
どれ、それなら参考にしてやるかな。ぼやきながら、ブラウン管に視線を移す。
『迷っていることがあれば、思い切って行動に移してみると幸運が。 本日のラッキーアイテムは、“電話の子機”
です。』
「電話の子機ぃ?」
「あら、何か問題でも?」
くすくすと笑い声。
「外に出かけるのに、電話の子機なんか持って行く人いないんじゃないのか。」
「だから、気休め程度ですってば。」
電話の子機を片手に、プロポーズはあるまい。
はあと溜息をついて、フォークを持ち直す。
あれだけ大きかったパンケーキは、あっという間にあとひとくちになってしまっていた。
―――『迷っていることがあれば、思い切って行動に移してみると幸運が。』
それにしてもこんな朝の他愛ない占いで、しかし大きな収穫を得たような気分になる僕は、顔と体格に似合わず、とことん意気地がないらしい。
「奈津子は、何位だった?」
しっかりチェックしておいたけれど、わざと聞いてみる。
「私は最下位でしたよ。『忘れられない一日になるかもしれません。』ですって。」
「へえ、この朝の占いてやつは、いつもそんなに大袈裟なのかい。」
「さあ、どうなのかな。」
笑う彼女に背を向けて、苦笑いする。
「最悪の日になるかもよ。」
「やだもう、ヘンなこと言わないでください。」
「いや、ありうるな。 大いにありうる。」
結婚て、墓場だっていうじゃないか。
タチの悪い男につかまってしまったと、諦めてくれるかい。
……特別なものは何もいらない。
ただ君がいればいい。
なんて月並みなセリフ、口に出せずに僕は笑う。
その代わりに、学生時代に流行っていたジンクスを思い出している。
二人っきりの時のオナラをゆるしてくれたら、婚約を切り出してもOKだって。
バカらしいけれど、何度も思い出してしまうのだ。
それじゃどれどれ、勇気を出して、ひとつ占ってみるか。
返事が聞きたくて、下腹に力をいれてみた。
待ってましたとばかりにおしりから、Bではじまるイヤな低音が響いた。
「…………。」
一瞬、テレビの音すら掻き消えたかのような沈黙。
「…………。」
ちいさく、彼女が息を飲んだのがわかる。
「す、すまん。」
やはりまずかったかと思った瞬間、
しかし、彼女はけらけらと笑い出した。
「いやだ、もうやめてよ貴博さん。」
眉をよせて、苦しそうにおなかを押さえて散々笑ったあとで、
悪臭警報発令、避難避難と、跳ねるように逃げていった。
――それは、OKと受け取ってもよろしいのでしょうか?
お、OKでしょ。 今のは。 オーケー、オーケーだろう。
…どのみち、 しわしわのじいさんとばあさんになって、
指輪のサイズが合わなくなっちゃう前に、
こればっかりは、僕が勇気を振り絞る番だ。
人気の無くなったキッチンリビングで、ひとり。
思い切るように、パンケーキの最後の一口を放り込んだ。
何かに理由をつけて、さんざん後回しにしていた。
だけど今日こそはきっと。
椅子を立って、大きく一つ伸びをして、恐る恐る戻ってきた彼女に、声をかけた。
「さーて、と。 着替えよう。 せっかくお互いに休みなんだし、出かけようよ。」
「ひょっとして、デートに誘ってるの?」
「1日デートもたまにはいいだろ。」
そうさ。 うんと派手なデートを用意して、勢いにまかせてしまおう。
星座占いは3位だし、ジンクス通りに行けば。
「そうねぇ。」
ほうら、奈津子さんも笑顔を隠せない。
歯磨きを終えて、クローゼットの奥にしまったリングケースを、着替えたばかりのジャケットのポケットに忍ばせた。
「おーい奈津子ー、まだかー?」
「もうちょっと待って。あとちょっとだけー。」
まったく、女ってのはどうしてこうも出かける準備が長いもんかね。
僕は鏡でもう一度髪型と髭をチェックして、それから大事なことを思い出した。
慌てて電話の子機の背面を開くと、そこから抜き出したバッテリーを、指輪と反対がわのポケットに忍ばせた。
動機はくだらないジンクス。
たのみは3位の星占い。
だけど、プロポーズはプロボーズだ。
口に出してOKをもらった瞬間から、二人は。
恋人という肩書きから、婚約者に変わってしまう。
今まで随分待たせたかもしれないけど、そこは仕方ないなと笑って欲しい。
「お待たせ。」
扉を開いて登場した奈津子に「そりゃこっちのセリフだ」といってしまいそうになって、慌ててごまかした。
「待ちくたびれたよ。」
「ごめんなさい。」
笑う彼女のその首に、普段はつけない真っ赤なマフラーを見つけて、僕は笑う。
それはおひつじ座の今日のラッキーアイテムだ。
「じゃあ、行こうか。」
今日のおひつじ座の運勢は12位。
『忘れられない一日になるかも。 単純なミスを犯さないよう気をつけて。』
そうだ。
一緒の墓に入るかどうかっていう、重要な問題が掛かってるんだ。
単純なミスには、気をつけてくれよ。
おひつじ座の恋人は、ラッキーアイテムの赤いマフラーがまとまらず、ちょっとまってと、すぐ後ろを追いかけてくる。
今日は、恋人最後の日。
そして、新しい一歩を踏み出す日。
口の中だけで笑って、僕は、扉を開く。
彼女にとって、忘れられない一日になるように。
おわり。
2010.11.23 再掲.(初掲載 2004年)
|

